「人材が集まらない」「せっかく採用しても定着しない」――中小企業経営者にとって深刻な課題です。
いま求職者、とくに若い世代が重視しているのは、給与や待遇だけでなく 「会社の価値観」や「社会的な意義」。
そこで注目されているのが、ESG(環境・社会・ガバナンス)をWEBでどう伝えるか です。
大企業のように分厚いサステナビリティレポートを作る必要はありません。
むしろ中小企業だからこそできる、等身大で共感を呼ぶ発信 が求職者の心を動かします。
実在する中小企業・ベンチャーの成功事例をもとに、どのようにWEBでESGを表現できるかを見てみましょう。
【採用サイト編】社員の声とSDGsで共感を呼ぶ ― 山翠舎の事例

長野県の株式会社山翠舎は、古木を再利用した空間づくりを手がける中小企業です。
採用サイトはコーポレートサイトとは別にありますが、人が中心となったとても魅力的なサイトです。
採用ページでは、社員のインタビューや現場写真を掲載
応募者は「ここで働くとどんな日常があるのか」を不安に思うもの。インタビューや現場写真はを「ここで働く自分」を具体的にイメージできます。
写真を掲載すると、顔が見えることで安心感が生まれ、社内の雰囲気や文化が伝わりやすくなります。このため、ミスマッチの防止にもつながります。
結果として、応募率の向上や定着率の改善 に効果を発揮します。
「古木を守ることが資源循環につながる」という理念をSDGsと結びつけて発信
山翠舎の企業理念を掲載することで、「ただの施工会社」ではなく「環境価値を生み出す会社」という差別化ができます。
求職者や取引先にとって、社会的意義のある仕事をしている企業は魅力的に映り、ブランドイメージの向上や共感の獲得 につながります。特に若手人材や意識の高い人材に響きやすいポイントです。
応募者にとって「この会社で働くこと=社会に役立つこと」というイメージを自然に持てる構成
近年の求職者、とくに 20代〜30代前半の若手世代 は、給与や待遇だけではなく 「やりがい」や「社会的意義」 を強く重視する傾向があります。
「どうせ働くなら、自分の仕事が社会や環境に良い影響を与えていると実感したい」というニーズが高まっているのです。
このような価値観を持つ世代に対し、
「この会社で働くこと=社会に役立つこと」というイメージを自然に伝えられる構成は、単なる採用広報ではなく 応募の決め手になる要素 となります。
さらに入社後も「誇りを持って働ける会社」という認識につながり、モチベーションの維持や定着率の向上 に直結します。
写真とリアルな空気感が、若手世代の共感を生む
採用ページのデザインにおいては、社員の笑顔や現場の様子を大きな写真で伝えること が重要です。
若手世代の求職者は「言葉だけの説明」よりも リアルなビジュアルや空気感 を重視し、そこから働く環境を判断する傾向があります。
また、テキストは長い理念説明よりも、短くシンプルなメッセージ の方が理解されやすく、印象に残ります。
さらに応募ボタンの前に「わたしたちと一緒に、資源を未来へつなぎませんか?」といった 共感型のひとこと を添えることで、求職者は「自分の価値観と重なる会社だ」と感じやすくなります。
【コーポレートサイト編】事業そのものが社会課題解決 ― アイデミーとボーダレスの取り組み
コーポレートサイト編では、大企業ではなく ベンチャー企業 を取り上げます。
ベンチャーは事業そのものが社会課題の解決と直結していることが多く、自然にESGと結びついた情報発信をしています。
その表現方法は大掛かりな仕組みを必要とせず、中小企業のサイトでもすぐに応用できる点が魅力 です。
また、採用力の強化や企業への信頼構築という観点でも、中小企業にとって良い見本になる部分が多く見られます。
ここでは、その中から特に参考になる2社をご紹介します。
アイデミー ― 教育で社会を変えるベンチャー企業
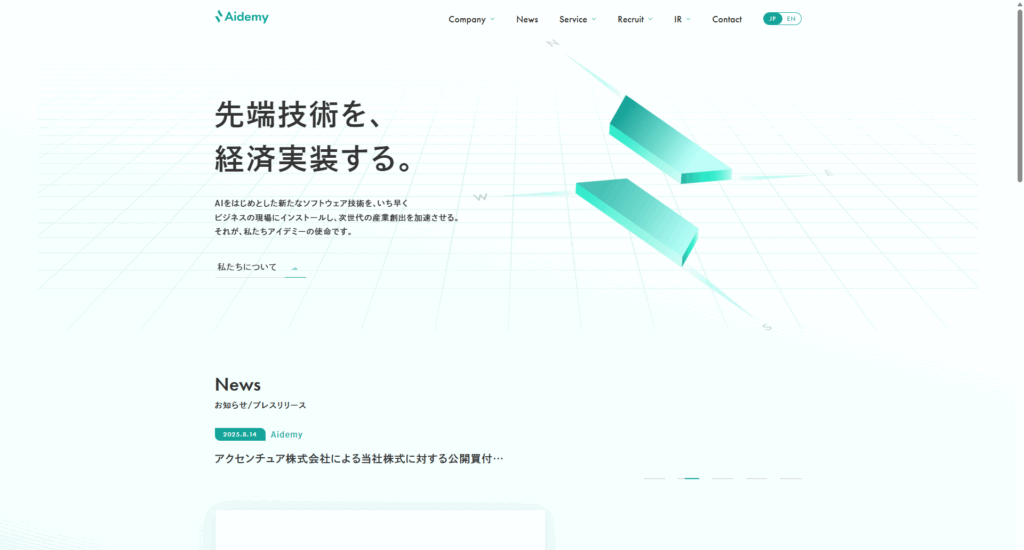
アイデミーは、AIやDXの教育サービスを提供するベンチャー企業 です。
企業研修から大学・自治体との連携まで幅広く展開し、地方のデジタル人材育成やカーボンニュートラル分野にも挑戦しています。
「教育を通じて社会課題を解決する」という理念を軸に、事業とESGを自然に結びつけている点が特徴です。
理念を前面に打ち出すメッセージ設計
サイトの冒頭から「教育で社会を変える」という強いメッセージを掲げています。
企業の存在意義を一目で伝えられるため、求職者や取引先に「この会社は社会的使命を持っている」と印象づける効果があります。
事業と社会課題をつなげるコンテンツ構成
教育サービスの紹介を「人材育成」「地域貢献」「環境対応」といった社会的テーマに結びつけて展開。
単なるサービス説明ではなく、「なぜこの事業が社会に必要なのか」 を自然に理解できる設計になっています。
採用・信頼構築に直結するわかりやすいデザイン
シンプルで見やすいレイアウトを採用し、サービスと理念の両方がストレートに伝わります。
難しい専門分野を扱いながらも、図解やキャッチコピーを活用して「誰にでも理解できる」工夫があり、信頼性と親しみやすさを両立 しています。
アイデミーのサイトは 「理念の強さ × 社会課題との接続 × 分かりやすさ」 を兼ね備え、見る人に直接語り掛ける力強さも持っています。中小企業のサイト作りにも応用しやすい好事例といえます。
ボーダレス・ジャパン ― 社会課題解決に挑むソーシャルベンチャー
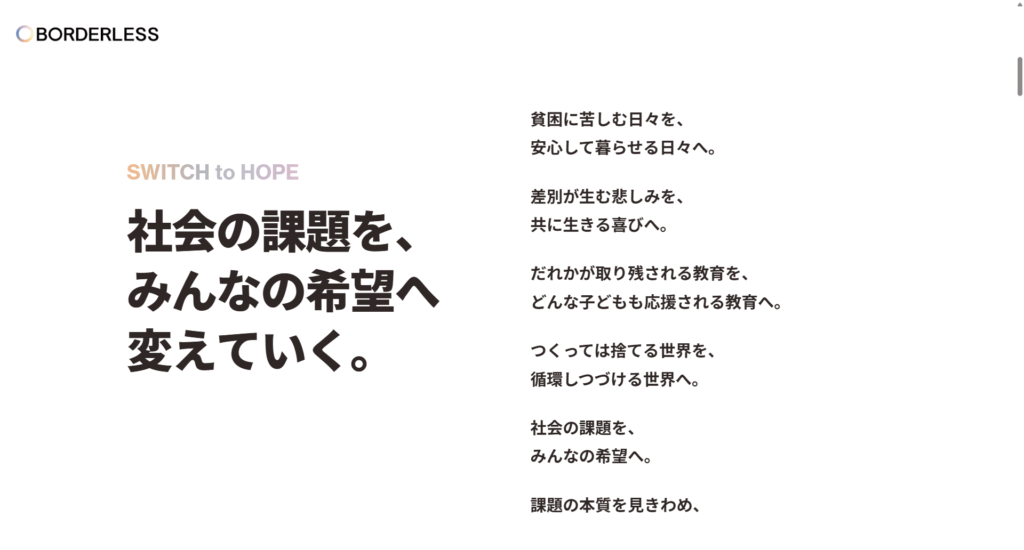
ボーダレス・ジャパンは、貧困、環境問題、教育格差など社会課題を解決する事業を複数展開するソーシャルベンチャー です。
自然エネルギー事業や再生PCの販売など、日常生活に直結するテーマを扱いながら、世界中で40以上の事業を立ち上げています。
「ソーシャルビジネスを通じて社会を変える」という理念を体現し、コーポレートサイトでもその姿勢が色濃く反映されています。
事業そのものがESGの取り組みになっている
ボーダレスの事業紹介ページでは、各プロジェクトが「環境」「貧困」「教育」など、具体的な社会課題に直結していることがわかります。
「何をしている会社か」だけでなく、「なぜそれが社会に必要か」 が伝わる構成になっており、ESGを後付けでなく自然に発信できています。
共感を呼ぶストーリー性あるコンテンツ
ボーダレスのサービス紹介は、単なるサービス紹介ではなく、創業の背景や事業立ち上げの動機など、人の想いにフォーカスしたストーリーが随所に盛り込まれています。
この語り口は、求職者やパートナーに「自分も一緒に取り組みたい」と思わせる力 を持っています。
グローバルに展開しながらも親しみやすいデザイン
世界40事業というスケール感を持ちながら、サイトのデザインはシンプルで視認性が高く、初めて訪れる人でも全体像を理解しやすい構成です。
写真やイラストを効果的に使い、社会課題という重たいテーマを身近に感じさせる工夫 がされています。
ボーダレス・ジャパンのサイトは、「事業とESGの一体化 × ストーリー性 × 親しみやすさ」 がポイントです。
中小企業が自社サイトでESGを発信する際にも、規模の大小にかかわらず参考にできる事例といえます。
【地域活動編】地域密着型の信頼を育む ― 小さな会社でもできる社会貢献発信
「地域活動の発信」は、大企業のようにCSR専用ページを構える中小企業が少なく、実際の事例もあまり表に出てきません。
さらに日本の中小企業には、「当たり前のことだからわざわざ発信しなくてもいい」という気質もあり、地域で良い取り組みをしていても伝えるのが苦手なケースが多く見られます。
実際に調べてみると、部分的に参考になるコンテンツはあるものの、「地域活動全体の発信がお手本になる」というWEBサイトは残念ながら見つかりませんでした。
だからこそ、ここでは「こうすれば無理なく伝えられる」という視点で、コンテンツの作り方を紹介します。
中小企業だからこそできる、日常のちょっとした活動や地域とのつながりを、そのまま伝えるだけで十分に価値があるのです。
地元の清掃活動や子ども食堂の支援を写真付きで紹介
地元での清掃活動や子ども食堂の支援を、写真と一緒に紹介するのもおすすめです。
社員が街をきれいにしている様子や、子どもたちと触れ合っている姿を見せることで、地域に根ざした会社であることや、社員が誇りを持って取り組んでいる姿勢を伝えることができます。
「当たり前のことだから」とあえて発信していない企業もありますが、実際に写真で見せるだけで、地域の人にも求職者にも強い共感を持って受け止められます。
小さな取り組みほど、会社の温かさや信頼感が伝わりやすいコンテンツ になります。
社員が地域イベントに参加している様子をブログ形式で掲載
社員が地域イベントに参加している様子を、ブログ形式で紹介するのも効果的です。
写真とともに「地域の方々と直接ふれあえた」「子どもたちの元気な姿に励まされた」といった社員の声を添えることで、会社の温かい雰囲気や地域に寄り添う姿勢が自然に伝わります。
特別な企画を立ち上げなくても、普段のイベント参加を記事にまとめるだけで、地域とのつながりを大切にしていることを発信でき、読む人の共感を得やすくなります。
小さな取り組みでも「地域に根差す会社」という信頼感を育てる
大きなプロジェクトでなくても、日常の小さな取り組みを紹介することはとても価値があります。
たとえば、社員が地域のイベントでお手伝いをしたり、商店街の活動に参加したりする様子を伝えるだけで、「地域に根差して一緒に歩んでいる会社だ」という信頼感 が育まれます。
発信する側にとっては些細に感じることでも、見る人にとっては会社の姿勢や温かさを感じ取れる大切な情報です。
こうした積み重ねが、地域の人や求職者からの共感につながっていきます。
明日から始められる「中小企業のためのESG発信チェックリスト」
- 社員の声を載せる(働く意義を共感で伝える)
- 事業を社会課題と結びつける(一言でも良い)
- 地域活動を紹介する(写真やブログで十分)
大切なのは、立派な資料ではなく「自社らしさ」。
「私たちはこういう想いで事業をしている」
「地域や社会のために、こんなことを続けている」
そうした発信を積み重ねることで、人材に選ばれる会社へとつながります。
御社のWEBにESGを取り入れる方法、具体例をご紹介します




